��]�̒a��
��慎h�̉�������
Seibun Satow
"I much prefer a
compliment, even if insincere, to sincere criticism�h.
Titus Maccius Plautus �gMostellaria�h
�@�ꔪ���I�̉p�����\����̑�Ȓm���l�}�[�^�C�i�X�E�X�N���u�����X���m�����̖��m�֖��̂܂���ʂ��������A�u����Ȃ��̂�慎h���ƌ����̂���?�܂��������������B��]�͂ǂ��ɂ������̂��H�v�ƒQ�����Ƃ��낤�B������A�ނ͌Í������̊w��ɐ��ʂ��A���̒m���̊m��������ⓖ�㐏��ƕ]���ꂽ�l��������ł���B
�@�f���}�[�N�́w�������Y�E�|�X�e���iJyllands-Posten�j�x���́A��Z�Z�ܔN�㌎�O�Z���A�C�X�����̗a���҃��n���}�h�̐���慎h������f�ڂ���B�������C�X�������������q���֎~���Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A�u�\���̎��R�v�ȂǍڂ������R�����Ă���B����ǂ��A���̃J���J�`���A�̒��ɂ́A���n���}�h�̃^�[�o�������e�Ƀf�t�H��������Ă�����̂��܂܂�A����͂��������������g���e�����Y����U�����Ă���A�������̓��X�����͖{���I�Ƀe�����X�g�Ȃ̂��ƌ�������ł���B�C�X�����ɂ�����ł��d�v�ȋ������q�̋֎~�ɔw���Ă��邾���łȂ��A�a���҂J�����Ƃ����킯���B�������A�_���e�E�A���M�G���́w�_�ȁx�̎���Ȃ�Ƃ������A������ꐢ�I�ɓ����Ă���B���ꂪ���E�ɓ`������ƁA�f���}�[�N�݂̂Ȃ炸�A���B�ŎӍ߂�v������f���������N��������A�C�X���������̐��{�E�_�w�ҁE���O����R�c��������ꂽ�肷��ȂNJe�n�ɔg�䂪�L����B���B�̊����}�̂̒��ɁA�m���E�G�[�̃L���X�g���n�G���w�}�K�W�l�b�g�iMagazinet�j�x�̂悤�ɁA�u�\���̎��R�v���f���A�����J���J�`���A��]�ڂ�����̂�������B�������N���Ă��������A�w�������Y�E�|�X�e���x�̓C�X�������k�̊�����Q����慎h��̌f�ڂ��Ӎ߂��A�����Ȃ�ꍇ�ɂ��^�u�[�������Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ��\����B
�@���_�̎��R�́A�p�A���n�����̃j���[���[�N�ŁA�ꎵ�O�ܔN�����A�V�����s�l�W�����E�s�[�^�[�E�[���K�[���ٔ���ʂ��ď����Ƃ��������ɗR�����Ă���B�ނ͐A���n���̕s������������L�����ڂ��A����𗝗R�ɓ��ǂ���i����ꂽ���A���_�v���̈Ӌ`�d���锆�R���͐V���̕��ɐ�������F�߁A���߂ɂ���B���̂悤�Ɍ��_�̎��R�͍s��������X���ɂ��錠�̗͂}���Ƃ��Đ��܂�A�s�g����Ă����̂ł���A���̋@�m�Ɍ����閟����f�ڂ��闝�R�Ƃ��ėp����̂ɂ͖���������B�hL�fironie est la bravoure des
faibles et la lâcheté des forts�h (A. Berthet).
�@���̎����́A�\���̎��R�����ꂽ�ƌ��������A���[���b�p�̒��ɂ���C�X�����Ɋւ���Ό��△�������I�悵���ƌ���ׂ����낤�B���̌�A���B�e�n�ŁA�C�X�����ɌW���\�������l����Ă��邪�A�����慎h�掖���ƕ\����̂ł���B���ꗬ���Ǝ��l�͓��{�ŕp�����錻�ۂł���ʂ�A�I�[���E�I�A�E�i�b�V���O�͋ɂ߂Ĉ��Ղȑ��҂ւ̗����⋤����������Ă���ɂ����Ȃ��B
�@�������A慎h�̗��j�͂��̌����̊m�������Â��B�ꎵ�Z��N�����l�N�܂ő������X�y�C���p���푈�ɍۂ��A�ꎵ���N�A�p���̃W�����E�A�[�o�X�m�b�g(John Arbuthnot)�͑t�����X�a���������咣���A�p���t���b�g�W�w�W�����E�u��(The History of John Bull)�x�����s����B���̃W���i�T���E�X�E�B�t�g�ƃA���N�T���_�[�E�|�[�v�̗F�l�͎Q�킵�Ă���e�����[�l�����A�p�����u�W�����E�u���v�Ɩ��t���Ă���B���̎��摜�́A�����Ŕ��Y�{���𗚂��A��_�Ȃ���A�C�����ŁA�C���������A�w�}�����̂��匙���ŁA���ƗV�тɖڂ��Ȃ��A�F����ɂ��A�u���h�b�N���]���Ă���Ƃ������̂ł���B���̃W�����E�u�����́A�����̃G�X�j�b�N�E�W���[�N�ɓo�ꂷ��C�M���X�l�ƈقȂ��Ă��邪�A�������g�ɑ���慎h�ł���A���̍s���g���p���I�ł���B��C�M���X�ł͎����̂��Ƃ����邱�Ƃ���Ϗd�v�Ť�t�Ɏ����̂��Ƃ����Ȃ��z�͖��Ƃ������͋C������B�p���self-deprecating(�Z���t��f�v���P�C�e�B���O)�Ƃ�����ڂ��͂���Ȋ��o����{��ŕ\�����鎞��"���}�I���[���A"�ƌ����Ă��邪�����"�}��"�Ƃ������������j���A���X���悭�Ȃ��Ƃ̎w�E�������Ƃ�����B��������deprecate�Ƃ����P��ͤ���l�ɑ��ĂȂ���{��Ɠ����Ӗ��ɂȂ邪��Ώۂ��������g�ƂȂ�Ƃނ���m��I�Ȉ�ۂ�^����(�s�[�^�[��o���J���w�ڂ��������郍�b�N����240�x)�B
�@慎h�́A��������d�Ȃ荇���ꍇ�����Ȃ��Ȃ�����ǂ��A�o�[���X�N�E�p���f�B�E�p�X�e�B�V���̎O�ɑ�ʂł���B�u�o�[���X�N(Burlesque)�v�̓C�^���A��̢���m��ɗR�����A�������ړI�őΏۂ�͕킷���@�ł���A�����ɂ̓��X�y�N�g�͂Ȃ��A���ӂƚ}������B���́u�p���f�B(Parody)�v�̓M���V�A��̢�ʂ̣̉���ꌹ�Ƃ��A�����悤�ɝ���ł��邪�A�͕킵�Ă��鎩�����g�����̑ΏۂƂ��Ă���_�ŁA�o�[���X�N������߂��킫�܂��Ă���B�Ō�́u�p�X�e�B�V��(Pastiche)�v�̓C�^���A��̢�����፬�������h�����A�Ώۂ����A�͕�̋Z�@���g�ɍł��S������A�����̍�i����̖͕���W�߂Ă��邱�Ƃ������A�u�₽���p���f�B(cold parody)�v�ƌ����Ă��悢�B���̃J���J�`���A�̓��X�����ւ̚}�肪���ĂƂ��A���̒��ł́A�o�[���X�N�ɑ����Ă���B�u�Ђ₩���Ƃ͕i�悭��������Ƃ��v(�A���X�g�e���X�w�C���w�x)�B
�@慎h�̓~���[�V�X���琶����B�������A���̎�@�͍Č��ł͂Ȃ��A�L�����ł���B慎h���쐬����ɂ́A�Ώۂ����̑��̂��̂ƈقȂ�ŗL����c�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�֍����e�p��̌`�̂܂�ňႤ�W���C�A���g�n���^����p�����āA���Ă���Ɗ�������̂́A���̒��g�v�����X���[�̋L����������Ă��邩��ł���B慎h�̓��@�[�`�����E���A���e�B�A���@�[�`�����e�B�̒Nj��ł���B�u���@�[�`����(virtual)�v�̔��Ό�́u���A��(real)�v�ł͂Ȃ��B�����(nominal)�������ɑ�������B���ڂ̗ދ`��͢���z(supposed)��⢋[��(pseudo)��ł���B�O�҂͉��ɑz�肵�����̂ł���A��҂͊O���͎��Ă��邪�A�{���I�ɂ͈قȂ���̂��w���B�܂��A���A���̔��ӌ�́A�����(real number)��Ƣ����(imaginary number)��̊W�������Ă���ʂ�A���(imaginary)��ł���B���@�[�`�����́A�ނ���A�����̗ދ`��ł���A����͕\�ʓI�ɂ͂��������Ȃ�����ǂ��A�{�����邢�͌��ʂɂ����Č�����������������̂��Ӗ�����B慎h�͂��̃��@�[�`�����e�B�̕\�������ł���A慎h��Ƃɂ͖��҂̍˔\���s���ł���B
�@慎h�͋L���ɂ���č\������A��҂Ɠǎ҂͂��̋L����ʂ��ă��b�Z�[�W�𑗎�M����B�K���𗹉����Ȃ���A�����n�삵�A��e����B��㐢�I�̉p���̏����ƃW���[�W�E�����f�B�X���u���������A�ǂ�ȏ������ŁA���̐l�Ԃ̐����x���킩��v�ƌ������悤�ɁA��M�������̃��b�Z�[�W�����ۂɁA�������g���L���Ƃ��đ��̐l�ɑ��M���Ă��܂��B慎h�́A���̂��߁A�L���̋K�����ʗp���Ȃ��W�ł͋@�\�����Ȃ��B慎h���^�ɕ\�ۂ��Ă���̂̓��[���ł���B
�@�����x�������قǁA�L���͒ʗp���鐢�E���L���A��蕁�ՓI�ɂȂ�B�ǂɁu���Ί�v�ƋL���ꂽ�W���́A���{�̊�����ǂ߂Ȃ����̂ɂ͉��̂��Ƃ������ς�킩��Ȃ����߁A�L���Ƃ��Ă̋@�\�͒Ⴂ�B���Ր��������قǗD�ꂽ�L���ł���B
�@慎h�́A���̋L�����̂��߂ɁA����Ȃ�慎h�ݏo�����Ƃ������ł���B�W�����E�Q�C(John Gay)�́w��H�I�y��(The
Beggar�fs Opera)�x(�ꎵ��)�́A���{��`�ᔻ���������x���g���g�E�u���q�g�́w�O���I�y���x�̃��`�[�t�ɂȂ脟���ނ̒����Љ�I���엝�_�͋L���Ƃ��Ẳ��N�ł��鄟���A���̌�A�U�E�t�[�̃{�[�J���X�g�̃��W���[�E�_���g���[���}�N�q�[�X���剉���A��Z���I�㔼�̎Љ�ꔪ���I�̃o���b�h�E�I�y���̐��E����퉻�����悤�Ȃ��̂�慎h���Ă���A
MACHEATH: So, it seems, I am
not left to my Choice, but must have a Wife at last.----Look ye, my Dears, we
will have no Controversy now. Let us give this Day to Mirth, and I an sure she
who thinks herself my Wife will testify her Joy by a Dance.
ALL: Come, a Dance----a Dance.
MACHEAT: H Ladies, I hope you
will give me leave to present a Partner to each of you. And (if I may without
Offence) for this time, I take Polly for mine.----And for Life, you
Slut,----for we were really marry'd.----As for the rest.--- -But at present
keep your own Secret.
(John Gay �gThe Beggar�fs Opera �gAct3 Scene17)
�@�L���ł���ȏ�A慎h�͞B���ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�L����ǂݎ��₷�����邽�߁A���Ȃ킿�L���̋K���̓K�p�͈͂��g�傷�邽�߁A�ꔪ���I�O����慎h��ƃE�B���A���E�z�K�[�X�͎ʎ��I��@��������Ă���B�L���́A������̂𑼂̂��̂Ƌ�ʂ���ړI�ŔC�ӂōŏ��͑I���B����ǂ��A����ɁA����͎Љ�E���j����тсA�\���˂��L���X�g�����w���悤�ɁA�ŗL����\�ۂ���V���{���ƂȂ�B�B���Ȃ����ŁA���b�Z�[�W���`���Ȃ��Ƃ���A����͋L���ł͂Ȃ��A�v�����ɂ����Ȃ��B
�@�����ŁA���łɋL���Ƃ��ē���̈Ӗ��������Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��܂܁A�}�����g���Ă�����i���A���{�ɏZ��ł���ƁA������B�\���������s���̂ł���A���߂ăW�[���EC�E�N�[�p�[���w���E�V���{�����T�x�Ŋm�F���邭�炢�̂��Ƃ͂��ē��R���낤�B
�@�K���́A�u�Öق̃��[���v�Ƃ������t������悤�ɁA���݉����Ă��邾���łȂ��A���݂��Ă�����̂������B慎h��Ƃ́A�����A���̐��ݓI�K�������݉������A�l�X�̏���U���B�ꎵ���I�㔼����ꔪ���I�O���̉p���͂܂��ɂ��������l��H�������w�҂�舕����Ă���B����́u慎h�̉�������(The Golden Age of Satire)�v�Ƃ��Ă�Ă���B�v���������ł���Ƃ̖��O�������Ă݂�A�W�����E�h���C�f���A�W���i�T���E�X�E�B�t�g�A�A���N�T���_�[�E�|�[�v�A�W�����E�Q�C�A�_�j�G���E�f�t�H�[�A�E�B���A���E�z�K�[�X�A���[�����X�E�X�^�[���A�G�v���C���E�`�F���o�[�X�A�T�~���G���E�W�����\���Ȃǖ����ɉɂȂ��B
�@��Z�l��N�A�X�`���A�[�g��Ύ�`�œ|�ł܂Ƃ܂����s�����s���[���^���v�����N�����B���̓���́A��Z�l��N�ꌎ�A�����`���[���Y�ꐢ�̏��Y�ňꉞ�̌���������B�����͔p�~����A�u�C�M���X���a��(Commonwealth of England)�v����������B
�@��Z�O�N�A�I���o�[�E�N�����E�F�����N�[�f�^�[���w�����A�c������U�����A���{�E�R�̍ō����E�̌썑���ɏA�C����B�ނ͎j�㏉�̌R���ƍَ҂Ƃ��ė��j�ɖ������ނ��Ƃɐ���B
�@��Z�ܔ��N�A���̎���A����p�������`���[�h�E�N�����E�F���͖��\���G�ɕ`�����悤�Ȑl���ŁA���N�ɂ́A���s�����Ȍ��͂���蓊���Ă��܂��B���ǂ��������钆�A���}�h�́A�}�i�I�Ȑ����h�ƑR���Ă������V�h���c��d����Ƃ��������Ō��������Ƃ��A�嗤�ɓ��S���Ĕ��R�����E�F���X�^���𑱂��Ă����`���[���Y�ꐢ�̎q���A��������B�ނ́A��Z�Z�Z�N�A�`���[���Y�Ƃ��đ��ʂ��A�������Â���������B
�@�Ƃ��낪�A���̃J�g���b�N�̍����́A���͂���ɂ���ƁA���̖̂ɂ���B�u����낢���v�Ǝv�������ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����A���낤���Ƃ��A�ނ͐�Ή����ւ̉�A�𐄂��i�߁A�c����y���������߁A�c��Ƌ{��Ƃ̑Η����G�X�J���[�g���Ă����B
�@��Z���ܔN�A�`���[���Y���S���Ȃ�ƁA�킪�W�F�[���Y�Ƃ��đ��ʂ���B�ނ����\���������A�j�̎q�������Ȃ��������߁A������E�҂�n��Ȃǂ̃g�[���[�h���������߂�c��͑Ό��p������߁A�����I�ɂł͂Ȃ��A�����w�I�ȉ����Ɋ��҂������Ă���B�������A����̎��s��҂��ă`�F�X���w�����l�͂��Ȃ��B�����N�A�j�q���a�����A����͗����Ă��܂��B�����ŁA�c��̓I�����_�̃I�����W���v�Ȃ������ɏ����Ƌc�����A�E�B����������������B���̓t�����X�̃��C��l���Ɛ푈���n�߂����肾�������A�O�i���������ς��A�I�����_�R�𗦂��ăC���O�����h�ɏ㗤���n�߂�B���̕��m�����W�F�[���Y�͍Q�Ăċc��ɏ���������������ǂ��A���ۂ����B�R�ɏo�����߂��o�����Ƃ������A�p���R�����ł��A�����̃J�g���b�N�D������ɕs��������Ă��镺�m�������A�퓬�ɉ����铮���������Ȃ��B�ǂ��l�߂�ꂽ�W�F�[���Y�̓t�����X�ɖS������ق������Ȃ��Ȃ�B���̌�̗��j�́A�����̓ƍَ҂����̏o�������狳�P���w���A���������͑��v�ƍ���������X���ɂ��邱�Ƃ������Ă���B���u���N�A���j�͂����̖������B���������s���͂��̖����v���𢖼�_�v��()Glorious Revolution��̖��ŌĂԂ��ƂɂȂ�B
�@��Z����N�A�I�����W���E�B���A���ƍȃ��A���́u�����̐錾(Declaration of Rights)�v������āA�E�B���A���Y�O���E���A���Ƃ��đ��ʂ��A�����������n�߂�B�s���[���^���v���Ɖ������ÁA���_�v����ʂ��A��Ή����̎���̓C�M���X�ł͂��͂�ߋ��̂��̂ƂȂ�B���N��A�����̐錾�𖾕��������u�����͓̏T(Bill of Rights)�v�ɂ��A�����͗��@�E�s���E�i�@�E�ېł̂��ׂĂɂ����ċc��̏��F��K�v�Ƃ��A���Ƃ̍ō��@�ւ͉����ł͂Ȃ��A�c��ւƕύX�����B
�@���̊ԁA�C�M���X�͎O�x�ɘj���ăI�����_�Ɣe���𑈂��Đ�������Ă���B��Z�܈�N�A�N�����E�F���͍q�C���𐧒肷��B����́A�C�M���X�Ƃ̏��i�A�o�����C�M���X�D�Ɠ������E�n��̑D���Ɍ��肵�đΊO�f�Ղ��m�ۂ���Ɠ����ɁA���p�f�Ղŗ��v���グ�Ă����I�����_����ߏo���ړI�Ɋ�Â��Ă���B�I�����_�͋����������A���N�A�����͐푈�ɓ˓�����B���̑�ꎟ(��Z�ܓl)�Ɏn�܂�A���(�Z�܄��Z��)�A��O��(�����l)�ƎO�x�ɘj���ĉp���푈���u�����邪�A����͊C�㌠�ƐA���n���߂��鑈���ł���B�p�����D���Ȃ܂܁A�����̓E�F�X�g�~���X�^�[�����������B�C��̔e���̓I�����_����C�M���X�ւƈڂ�A�j���[�A���X�e���_�����j���[���[�N�Ɖ��̂����悤�ɁA�V�嗤�̃I�����_�̂͂قƂ�ǂ��p�̂ƂȂ�A�I�����_�̐Ⓒ���͖����}����B
�@���������C�M���X���߂��鍑���O�̕ω��ɂ��A�����_�Ƃ���g�����̃q�G�����L�[�����ꄟ�������܂Ő�Ύ�`�I�q�G�����L�[����̂��������ŁA���ꎩ�g�����S�ɏ��ł��Ă��Ȃ��ɂ��Ă������A�C�O�A���n����c��ȗʂ̕��Ə�������Ă���B���ׂĂ��������ɉp���ɑ͐ς��Ă����B�������A�A�_���E�X�~�X�́A�������I�����̕���Ǝ��{��`�̐i�W��O�ɁA���������B�u�w���R���C(laissez-faire)�x�ɔC����v�B�s�����n���ł͂Ȃ��B�����A���������������Ă����B
�@�p����慎h���w�͂��̍��ׂƋ��ɔ��B���Ă���B���E�F�i���X��慎h�͂��ׂĂ������Ƃ��݂���������Ă����悤�ɁA����́A����ׂ������튯�������Ă���A�c��Ȗ������ȑ͐ϕ������ݍ��߂�B慎h�́A�L�����̃~���[�V�X�̍�Ƃ�ʂ��āA���ׂɐ��݂��Ă���K�������݉������A������^����B慎h��Ƃ͖c��ȏ����L�������āA��i�Ɉ��k�E�ۑ�����B�����A�s���~�b�h�^�̒�����˂��A�����邽�߁A���Ƃ��āA���ꂪ�G�R�Ƃ��Ă���A�O���e�X�N�ł��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�@���̂悤��慎h��n�삷���Ƃ����Ȃ₩�ł���Ɠ����ɂ��������ł���B�ނ�́A��p�ɁA��i�������x�ɁA�W�����������̂��g��������B����ɁA�Љ�I�E����I�ω��ɉ����āA�����I�E�@���I�ɗՋ@���ςȎp�����Ƃ��Ă���B����̓J�����I���ł���B
�@�W�����E�h���C�f��(John Dryden)�̎v�z����慎h�̉�������̋C�����悭������Ă���B�ނ́A��Z�ܔ��N�ɖS���Ȃ����썑���I���o�[�E�N�����E�F����Ǔ����鎍�Œ��ڂ��ꂽ�ɂ�������炸�A�Z�Z�N�ɉ������Â���������ƁA��]���ĉ�����`�҂ƂȂ�A�����`���[���Y�̕��A���j���āw���P�ėՁx(��Z�Z�Z)�Ɓw���ʎ��ɂ����荑���É��ɕ����x(��Z�Z��)��\�킵�Ă���B�Z�O�N�A�ނ̃p�g�����ł���A�{�쌀��Ƃ̃��o�[�g�E�n���[�h�̖��G���U�x�X�ƌ������Ă���B
�@��Z�Z��N�A�h���C�f���͂��悢���������߂āA�Y�Ȃ������n�߂�B�Z�l�N�̔ߊ쌀�w���G�x�Ő������A���ꂩ���Z�N�ԁA�p�����\���錀��Ƃ̖������L�[�v����B�����A�Ќ��E�̕����������A�@�m�Ɛ������Ɉ�ꂽ�u���K�쌀(Comedy of Manners)�v���{�쒆�S�̊ϋq�ɍD�܂�Ă���B�������A�h���C�f�����̍앗���ΎG�ŁA����ȓ��e�����Ȃ��Ȃ��A�Ƃ��Ƃ��w�e�ȒU�߁A�܂��̓����o�������x(��Z����)���A���i�Ƃ������R�ŁA����u�̎���̓��ǂ���ٗ�̏�f�֎~�̑[�u���Ă���B
�@�������Ê��́A�s���[���^���̎x�z�ɂ��֗~��`�̔����ƍ����̐ߐ��̂��̎����Ȃ��ґ�E�����O���̐�������A�|�p��i�ɃG���O���i���Z���X���悭�`���ꂽ����ł���B���X�̂��Ƃł͓��ǂ��K�����Ȃ��������A�h���C�f���͉H�ڂ��͂��������Ă���Ɣ��f����Ă���B
�@�����܂ł��Ȃ��A�h���C�f���͔��ȍ�i���������M���Ă����킯�ł͂Ȃ��B���̕���ɂ����Ă��A��z�����˔\�����Ă���B�����̍�i�͉C���މ��y�I�ȌX�����������������A��ɖ��C�����������Ă���B���ł��A�w���ق̔N�x(��Z�Z��)�ł́A�O�N�ɋN�����C�M���X�C�R�ɂ��I�����_�R���j�ƃ����h�����`���A�Љ�I�S�̍����������Ă���B�܂��A�E�B���A���E�V�F�[�N�X�s�A�́w�A���g�j�[�ƃN���I�p�g���x�����`�[�t�ɂ����w���ׂĂ͗��̂��߂Ɂx(��Z����)�́A�������Âɂ�����ߌ��̍ō�����̈�Ɛ������Ă���B�Z���N�A�u�j�����l�iPoet Laureate�j�v�ƔF�߂��A���̓�N��A�����N��L�Ҏ[���ɔC�������B
�@�h���C�f���́A��Z����N�A�w�A�u�T�����ƃA�L�g�t�F���x��n�삵�A慎h���ւƊ����͈͂��L����B�p�Y�ΉC��ɂ�邱�̎��́A�����̓o��l���Əo������p���āA�c����h�̃z�C�b�O�}���������`���[���Y�̒탈�[�N���łȂ��A�����}�X�������̉����ɏA���悤�Ƃ��������I�A�d��慎h���Ă���B�ނ�慎h���ł��l�ڂ��䂩���ɂ͂����Ȃ��B�z�C�b�O�h�̌���ƃg�}�X�E�V���h�E�F����ɗ��慎h�������w�}�N�t���N�m�[�x�i��Z����j�̓A���N�T���_�[�E�|�[�v�̃p���f�B���w��l��`�x�ɉe����^���Ă���B
�@���R�A�h���C�f���ɑ��A���ɐ������ˁA�����d�Ԃ������Ă��Ƃ����v���ɂ���ꂽ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��B��Z����N�A����o�b�L���K�����̓o�[���X�N�Y�w���n�[�T���x�������A�h���C�f�����������낷�B����̎�̓���\�I���A����𒃉����̂͂��̎���ɂ悭�������@�ł���A����́u������(Play-within-a-play)�v�ƌĂ�Ă���B���̃��n�[�T�����͌���Ƃ��čD�]�ɂȂ������̂́A�������̒j���M���t���ƌ��킹��܂łɂ͎���Ȃ��B
�@��������慎h��Ƃɂ́A�ǂ���Ƃ��Ȃ����������邱�Ƃ��t�����ł���B���ɁA�����̌|�p�Ƃ́A�S�ʓI�ɁA����ȍ��Y�����L����p�g�����̐����I�E�o�ϓI�Ȕ�̉��Ɋ������Ă��邽�߁A�x���҂̗����z����������Ȃ�Ȃ��B�h���C�f�����A��͂�p�g�����̂��@���˂邱�Ƃ܂ł͂��Ȃ��B�������A�A���N�T���_�[�E�|�[�v(Alexander Pope)�͂���������S��������\�Ԃ��������A������߂̂Ȃ��O��I��慎h���ѓO���Ă���B�ނ̓h���C�f���̎�@�������p���ʼnp�Y�ΉC���p���A���������ꂽ�`���Ɋ��������Ă���B�������A�|�[�v�̓p�g�������������A�C�M���X�j�㏉�̎��������E�ƍ�Ƃł���B�ނ̓|�[�v�̓z�����X��|�A���̗��v�Ōo�ϓI��Ղ��m�ۂ��Ă���B�����A���̔̔��@�͍����̊��K�Ƃ͈قȂ��Ă���B����́A�o�ŋƎ҂�����ꂽ�{���Ҏ��g���\��҂ɑ���ƈ��������Ŕ̔�����Ƃ������@�ł���A�����Ă݂�A��Ƃ͕������X�ł���B����������Ƃ̃|�[�v�́A����ɂ��A�C���˂Ȃ��A�h煂ɖ��\��s���A���\�A�U�P��慎h���Ă����B
What dire offence from am'rous
causes springs,
What mighty contests rise from
trivial things
(Alexander Pope �gThe Rape of the Lock�h)
�@�|�[�v�́A�Љ�ɂ͂т��邠��Ƃ������݂�ڗ�A�Ȋw��\���o�����߂ɁA�X�N���v�����X�E�N���u(Scriblerus Club)�̒��ԂƋ��Ɂu�}�[�^�C�i�X�E�X�N���u�����X�iMartinus Scriblerus�j�v�Ƃ����ˋ�̐l�����l�Ă���B�ނ�́A�ꎵ�l��N�A���̎���w�҂ɂ��w�}�[�^�C�i�X�E�X�N���u�����X�̉�z�^(The Memoirs of Martinus Scriblerus )�x�����s���A���t�̃��[�u�E�S�[���h�o�[�O�Ƃ������ׂ��w�҂��Ƃ�}����B
�@��Z���ܔN�A���̃��[�N�����W�F�[���Y�Ƃ��đ��ʂ���B���̃J�g���b�N���k�͋c��Ɩ��O�̔��Ɏ���݂����A�Z�̎��𗝗R�ɉ����ɔ��A�ꐧ���������s����B�h���C�f���́A���w���M�k�̏@���x(��Z����)�ɂ����Ď��g�̃v���e�X�^���e�B�Y���𐳓������Ă������A���ܔN�A�����A�J�g���b�N�ɉ��@���A���w�Ď��ƕ^�x(��Z����)�ŐV���ȐM��ٌ삵�Ă���B�����N�ɖ��_�v�����N����A�v���e�X�^���g�̃E�B���A���O�������ʂ��p����������ǂ��A�ǂ��������Ƃ��A�ނ͉��@���Ȃ��������߁A�j�����l�̒n�ʂƉ����������Ă��܂��B
�@�����ŁA�h���C�f���͋Y�Ȃɖ߂�B�������A�p�b�Ƃ��Ȃ��������Ƃ�����A�|��ɕ����]������B�ނ͌l�ŌÑネ�[�}�̃E�F���M���E�X��S�A��Z�㎵�N�A�w�E�F���M���E�X�S�W�x�����s���Ă���B�ނ̖|��́A����̊���猩��֗~�I�ƌ��������A�n�삪���荬�����Ă��邪�A�|�ɂ߂đn���I��Ƃł��邱�Ƃ�����������B�z�����X��I�E�B�f�B�E�X�A�W�����@���j�E�{�b�J�b�`���A�W�F�t���[�E�`���[�T�[�̍�i���C�����g���Ė|�Ă����w�Í����b�W�x(�ꎵ�Z�Z)���A���̉�������ŁA������Ă���B
�@�W�����E�h���C�f�����A�ꔪ���I�����邱�ƂȂ��A�ꎵ���Z�N�A�i�����Ă���B����́A�I�X�J�[�E���C���h����Z���I�̒��O�ɂ��̐��������Ă������̂Ɠ��l�A���慎h�ƌ����Ȃ����Ȃ����낤�B
From Harmony, from heavenly harmony
This universal frame began:
(John Dryden �gSong for St. Cecilia's Day�h)
�@�h���C�f���Ɍ��炸�A慎h�̉�������̍�Ƃɂ̓G�s�\�[�h�������A�����慎h��̌����Ă���B�h Great wits are sure to
madness near allied, and thin partitions do their bounds divide�h(John Dryden �gAbsalom and Achitophel").�T�~���G���E�W�����\���͋ɓx�Ɏ��͂��キ�A�܂��Ńy�[�W��|������悤���{��ǂ�ł���B�����ɃL����̂Œm��ꂽ�A���N�T���_�[�E�|�[�v�́A�a�C�̌��ǂɂ��A���l��̐g����137�����قǂ����Ȃ��A�������A���������ɂɋꂵ�߂��Ă���B�W�����E�Q�C�͗D�_�s�f�Ȓj�ŁA�l�̈ӌ����x�ɍl�����h�ꓮ���Ă���B���ネ�`�F�X�^�[�����ƃW�����E�E�B�����b�g�̓A���R�[���ɓM��A���D�ƕ����𗬂��Ȃ�����A�U������Ă���Ȃ�������f�v���A�h���C�f���ɖ\��������������悤�Ȃ��Ƃ����Ă����āA�ՏI�̏��ł��ׂĂ��������߂Ă���B
�@�܂��A�W���i�T���E�X�E�B�t�g(Jonathan Swift)�́A�ǂ��܂Ŗ{�C�Ȃ̂��킩��Ȃ����̂悤�Ȏ��g�̕����������Ă���B
Hic depositum est corpus
JONATHAN SWIFT S.T.D.
Huyus Ecclesiae Cathedralis
Decani
Ubi saeva indignatio
Ulterius
Cor lacerare nequit
Abi Viator
Et imitare, si poteris
Strenuum pro virili
Libertatis Vindicatorem
�@����ɁA���[�����X�E�X�^�[��(Laurence Stern)�͑��l�̂��߂ɓ��������Ȃ��Ƃ������R�Ŏ��M�����ɓ��������̂́A�����Ɣ��ڂ��A��e�̋��~���ƍȂ̐��_����ɔY�܂���Ă���B
�@���̔ނ́w�g���X�g�����E�V�����f�B(The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman,)�x(�ꎵ�Z�Z���Z��)�ɂ͕��������łȂ��A��Z���l�Z�͂̒��Ɏ��̂悤�ȃC���X�g�܂ő}������Ă���B
[ 152 ]
I Am now beginning to get
fairly into my work; and by the help of a vegitable diet, with a few of the
cold seeds, I make no doubt but I shall be able to go on with my uncle Toby's story, and my own, in a tolerable
straight line.
Now,
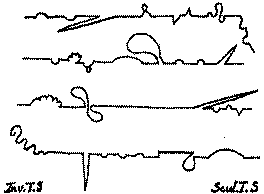
These
[ 153 ]
These were the four lines I moved in
through my first, second, third, and fourth volumes.-- In the fifth volume I
have been very good, -- the precise line I have described in it being this :
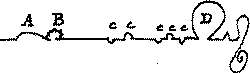
By which it appears, that
except at the curve, marked A. where I took a trip to Navarre, -- and the indented curve B. which is the short airing
when I was there with the Lady Baussiere
and her page, -- I have not taken the least frisk of a digression, till John de la Casse's devils led me the
round you see marked D. -- for as for c c
c c c they are nothing
but parentheses, and the common
ins and outs incident to the lives of the great-est ministers of state ; and
when com-
pared
�@�h���C�f���́A�w慎h�̋N���Ɣ��W�Ɋւ���_�l(A Discourse Concerning the Original and Progress of Satire)�x(��Z��O)�ɂ����āA�u慎h�isatire�j�v�̌ꌹ�Ƃ��ē�����Љ�Ă���B��̓M���V�A�_�b�́u�T�e�����X(��ά�у҃σ̓�)�v�ɗR��������ł���B�T�e�����X�̓f�B�I�j���\�X�̏]�҂ł���A�㔼�g�͐l�Ԃ����A�����g�͎R�r�̎p�����Ă���B�R�r�͑��Y�̂��߁A���m�ł́A�D�F�Ƃ����Ӗ���тт�B慎h�͈���ȗ��s�C�������͂��ł���킯���B
�@������̓��e����́u�l�ߍ���(satura)�v���ꌹ�Ƃ�����ł���B����������̂��̂������܂��Ȃ��ɋl�߂��̂�慎h�ł���A���̖{���́A�h���C�f���ɂ��A�u����(Mixture)�v���邢�́u��������(Hotchpotch)�v�ł���B
�@�T�~���G���E�W�����\�����W�����E�h���C�f�����u�p����]�̕�(Father of English Criticism)�v�ƌĂ�ł���悤�ɁA����������̋N�������݂���慎h�����]�����܂��B�T�e�����X����т����Ȃ������������ȍ앗�Œm����ނ������ł���Ƃ���A��]���ΎG�ɂȂ炴��Ȃ��B
�@���̓�̗v�f��������慎h�̌��^�͋I���O�O���I���j�b�|�X�ɋ��߂��悤�B�������A�s�K�ɂ��A�ނ̍�i�͑薼�ȊO�������Ă��Ȃ��B�K�^�ɂ��A���L�A�m�X���ނ���l���Ƃ���慎h��i�������Ă���A�����ɖ����Ȑl������������`���Ă���B�������A������������慎h�ɂӂ��킵���B慎h�̉�������̍�i�́u���j�b�|�X�I慎h(Menippean Satires)�v�Ƒ��̂ł���B
�@慎h�̃~���[�V�X�͑Ώۂ̌ŗL����c�����Ă��Ȃ���ΗL���ł͂Ȃ����߁A���̖{����ᔻ�I�ɕ��͂���K�v������B��]�Ƃɂ��A慎h��Ɠ��l�A�o�D�̍˔\���s���ł���B�t�ɁA慎h�ɂ���ČŗL�����̊��ł���ȏ�A��]��慎h�̔\�́E�菇�܂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��]�́u�������ϔ�]�v�A���Ȃ킿�u�n�b�`�|�b�`�E�N���e�B�V�Y��(Hotchpotch Criticism)�v�Ƃ��Ēa�������̂ł���B
�@�h���C�f���̑�\�I�Ȕ�]�w�����_(Of Dramatick Poesie: An Essay)�x(��Z�Z��)��慎h�I��]�A�ʖ��n�b�`�|�b�`�E�N���e�B�V�Y���̖͔͗�ł���B�h���C�f���͌Í������̕�������E���Ή����A���ׂĂ�y�U�ɍڂ��Ă���B�ꔪ�Z�ܔN�Z���̑�p���푈�̍Œ��A�������ăe���Y��ŏM�V�т�����l�l�̕��w�҂ɂ��V���|�W�E���Ƃ����ݒ�ŏ�����Ă���B�w�I�Y�̖��@�g���x���l�A�o��l���ɂ̓��f�������āA���ꂼ��ɈӖ��[�Ȗ��O�������Ă���B�ߑ㕶�w���^����u���[�W�j�A�X(Eugenius)�v�́u���܂�悫�l�v�ɗR�����A�����̒��b�`���[���Y�E�T�b�N���B���ł���A�ÓT�����^�̕��w�Ɨ͐�����u�N���C�e�B�[�Y(Crites)�v�́u�ᔻ�ҁv���w���Ă���A����҂Ńh���C�f���̋`�Z���o�[�g�E�n���[�h�A�t�����X�̐V�ÓT��`�ɌX�|����u���V�f�B�A�X(Lisideius)�v�̓R���l�C���́w���E�V�b�h(Observations sur le Cid)�x���Î������A����ƃ`���[���Y�E�Z�h���[�A����Ɂu�l�A���_�[(Neander)�v�́u�V�����l�v���Ӗ����A�h���C�f���{�l�ł���B
�@Neander was pursuing this Discourse so
eagerly, that Eugenius had call'd to
him twice or thrice ere he took notice that the Barge stood still, and that
they were at the foot of Somerset-Stairs,
where they had appointed it to land. The company were all sorry to separate so
soon, though a great part of the evening was already spent; and stood a while
looking back upon the water, which the Moon-beams play'd upon, and made it
appear like floating quick-silver: at last they went up through a crowd of
French people who were merrily dancing in the open air, and nothing concern'd
for the noise of Guns which had allarm'd the Town that afternoon. Walking thence
together to th Piazze they parted
there; Eugenius and Lysideius to some pleasant appointment
they had made, and Crites and Neander to their several Lodgings.
�@�����A�I�����_�͉��B�ōł��ɉh���Ă����o�ϑ卑�ł���A�C�M���X�͂���Ɏ���đ��낤�Ƃ���V�����͂ł���B�C�M���X�͑c�����S�̊�@�ɂ������̂����A������悻�ɗD��ɕ��w�𑽗l�Ȋϓ_�����荇���Ƃ����̂͂܂������S�����B
�@���̏��q�X�^�C����慎h�̔�]�̓����������Ɏ����Ă���B�����_���x���Ă��A�����_�Ƃ��ăq�G�����L�[���\�z���邱�Ƃ͂Ȃ����A��������Ă������Ƃ��Ȃ��B�����͐����ɕ��ׂ��Ă���B��҂͏����_�����ɔz�u���Ă������Ƃɔ\�͂𒍂��ł���B
�@����ւ̈�u�Ɋ�Â��Ă���ȏ�A�����łȂ���A慎h�̔�]���������Ƃ͂ł��Ȃ��B�Í������̒m�����n�m���Ă��Ȃ��ŁA��]�ƂɂȂ�͂��Ȃ��B��Ƃ͕��������ł���A�����S�ȑS���ł���B���p�́B�ǎ҂ɛZ�т邱�ƂȂ��A�����Ŗc�傩�����ɍs���A�����ǎ҂����̌����m��Ȃ������Ȃ�A�Â�����邱�ƂȂ��A����ׂ�ׂ����낤�B�㒎�ɓǏ����鎑�i�ȂǂȂ��B�ڂ̑O�ɂ���̂́A�m�I�̗́E�����ɖ�����煘r�̔�]�Ƃ��L�����{�ł���B���ȍ�i�ł͂Ȃ��B�S���ăy�[�W���J�����Ƃ��B�Ėڟ����W�����E�h���C�f���ɐK���݂����悤�ɁA��]�Ƃ͓ǎ҂����|���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@����ǂ��A���̎����慎h��Ƃ́A�P�c�̌�������������ƈႢ�A�Ƒn�����C�ɂ��Ȃ��B���쌠���ŃV�X�e�����m�����Ă��Ȃ��������炾���ł͂Ȃ��B慎h�͓Ƒn���ɕ߂���Ă����̂ł́A���藧���Ȃ����炾�B慎h�͎��Ȃ̕������Ɋ�Â����w�ł���B�u��]����Ƃ͎��Ȃ���鎖�ł���B���l�̍�i���_�V�ɂ��Ď��Ȃ���鎖�ł���v(���яG�Y�w�A�V���ƋT�̎q�U�x)�B����ق�慎h�̉������ォ�牓���ӌ��͂Ȃ��B
�@������慎h�͉���������Ƃ��Ă����ʂ��Ă���B�g�}�X�E�`���^�g��(Thomas Chatterton)�́A�����̕��̂�͕킵����n�삵�������ˋ�̈�ܐ��I���l�g�}�X�E���E���iThomas Rowley�j��Ƃ��Ĕ��\���Ă���B�������A�s�[�^�[�E�A�N���C�h�iPeter Ackroyd�j���ނ̍ˋC�܂��āw�`���^�g���U��(The Diversions of Purley)�x(��㔪��)�����s���Ă���悤�ɁA����Ȃ�p�X�e�B�V���̌���Ɛ�^�����͂����낤���A�قǂȂ����ꂪ��삾�ƃo���Ă��܂��A�ꎵ���Z�N�A�ꔪ�Ŏ��E����B
Wouldst thou kenn Nature in her
better parte?
Goe, serche the logges and
bordels of the hynde ;
Gyfe theye have anie, itte ys
roughe-made arte,
Inne hem you see the blakied
forme of kynde.
Haveth your mind a lycheynge of
a mynde?
Woulde it kenne everich thynge
as it mote bee;
Woulde ytte here phrase of the
vulgar from the hynde,
Wythoute wiseegger wordes and
knowlache free,
Gyf soe, rede thys, whych Iche
dysporteynge pende,
Gif nete besyde, yttes rhyme
maie ytte commend.
(Thomas Rowley �gEclogue the Third�h)
�@��������慎h�I��]�̐��_�����T�⎫���̍쐬�𑣂����͎̂��R�̗��ꂾ�낤�B����͂܂��ɋL�������ɔz�u���Ă���B
�@��Z�Z�Z�N�A�����h����������n�������B���㑍�كg�}�X�E�X�v���b�g(Thomas Sprat)�́A�w��������j(The
History of the Royal Society)�x(��Z�Z��)�̒��ŁA����ł͌��t�́u�V���v����(simplicity)�v���ł����ƌ����Ă���B���̃x�[�R����`�҂ɂ��ƁA���ꂩ��̊w�҂͌֒���E���A���������Ԃ������̂�˂��A�����̐l�����t��ʂ��ė��������L�ł���悤�ɁA�Ȍ��ōT���ځA�f���A���m�A�����ȏ��q�ȐS�����A����ɁA���t�̈Ӗ��Ɨp�@�ꂵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������Âɂ�������炸�A���̎咣�ɂ̓s���[���^�j�Y���̉e����������B
�@�T�~���G���E�W�����\��(Samuel Johnson)�̉p�ꎫ���͉�������̖ڕW�̃p���f�B�ł���B�����̉p��͒P��̒Ԃ���܂��܂��ŁA�K����n��ɂ�锭����p�@�̈Ⴂ���������A���̏̓A�i�[�L�[�ƌ����Ă��ߌ��łȂ��B����͉p��ɂ����铝�ꉤ������Ă��킯�����A�ނ͉p��̗������������������̂ł���A���̌��тɂ��A�ނ͋ߑ�p���������j�Ə^����Ă���B�Ȍ�A�ނ̎������p��̋K�͂ƂȂ������ʁA�hdramatick�h�ƃ��[�v���E�\�t�g�ŒԂ�ƃX�y���E�~�X�̌x�������}�����̂�ނ̂����ɂ���͍��ł���Ƃ��Ă��A���l�����킢�ł��܂����̂͊m���ł���B
�@�T�~���G���E�W�����\���͉p�ꎫ�T��Ҏ[����ۂɁA���^��̐������A�����@���m�����A���̗p��ɂ͌Í������̕������猵�I���Ă���B�ꎵ�܌ܔN�Ɋ��s���ꂽ�w�p�ꎫ�T(A Dictionary of English Language)�x�̓��l�T���X������ꔪ���I�܂ł̉p��̕��I���邢�͈��p�W�ł�������B�����ɂ��A�s�芥����p���Ă��邪�A��ɂƂ����l�͂��̎������p�ꎫ���ɂ�����芥���Ƃ��]����B����Z�l���g���Ă������̂́A�W�����\�����m��.�c��ȓǏ��ʂɗ��ł����ꂽ���ٓI�Ȓm�������p���A�قړƗ͂Ŋ��������Ă���B
�@It is the fate of those who toil at the
lower employments of life, to be rather driven by the fear of evil, than
attracted by the prospect of good; to be exposed to censure, without hope of
praise; to be disgraced by miscarriage, or punished for neglect, where
success would have been without
applause, and diligence without reward.
(Samuel Johnson �gPreface to a Dictionary of English Language�h)
�@�ނ́A�p���̖@�̌n�̔@���A�p�P��̌ꌹ�Ƃ��̗p�@�̕ω�����j�I�E�o���I�ȁu�����v��ςݏd�ˁA�q�G�����L�[��r�����Ă���B���̕Ҏ[�̕��j�́A�I�b�N�X�t�H�[�h�p�ꎫ�T�Ȃǂ��̌�̉p���̎����Ɏp����Ă���B
�@�T�~���G���E�W�����\���́A慎h�̉�������̒m���l�炵���A�p�ꎫ�������łȂ��A������̋K�͂����Ă���B�W�����\���̒�q�̈�l�W�F�C���Y�E�{�Y�E�F��(James Boswell)�́A����ɂ����ƈ��p����ɂ͂����Ă����̖��������ԁw�T�~���G���E�W�����\���`(The Life of Samuel Johnson)�x(�ꎵ���)�킵�Ă��邪�A����͋ߑ�`�L���w�̏o���_�ł���B
�@�gWhen a man is tired of
�@�gHell is paved with good intentions�h.
�@�gPatriotism is the last refuge of a
scoundrel�h.
�@�������A�p����慎h�̉�������́A�c�O�Ȃ���A���[���b�p�ł̕����I�w�Q���j�[�̒����ɂ�����P���ł���B���̎���̐��_�͎Y�Ɗv���ɂ�萢�E�ōŐ�[�̎��{��`���Ƃł͂Ȃ��A�܂������B�̑嗤�ň����p����Ă����B�h All human things are subject
to decay, and when fate summons, monarchs must obey�h (John Dryden �hMacFleknoe�h).
�@�X�B�́A�w���w�̗��j�x�̒��ŁA�ꔪ���I�̉��B�ɂ�����C�M���X�����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�C�M���X�͂������Ɂu��i�I�v�ł��������A���b�N�ƃj���[�g���͈ꔪ���I�W���̋P���̐��������B�t�����N������y�C����ʂ��āA���ꂪ�A�����J�Ɨ��̋N���͂ɂȂ������肩�A�����e�X�L���⃔�H���e�[����ʂ��āA�[�֎�`����t�����X�v���ɂ܂ł�����v�z�I�����͂ł��肳�������B�������A���ۂ́A���̎���ɂ̓C�M���X�̓��[���b�p�����̉�������]�����������B
�@�W�����E���b�N�ƃA�C�U�b�N�E�j���[�g���̎���́A�u�C�M���X�����𐢊E�ō��̈ʒu�ɂ̂����v�B�������A�嗤�ɑ���p���̕����I�D�����́B�o�ϗ͂̐i�W�Ƃ͔���Ⴗ�邩�̂悤�ɁA�ꔪ���I�ɐ����Ă����B���̕����̉Ԃ͉p���Ō͂�A���̎킪��嗤�A���Ƀh�[�o�[�C�������t�����X�ō炫�����B
�@�ꔪ���I�A�t�����X��Ǝ莆�̃l�b�g���[�N�ɂ��u���|���a��(Republic of Letters)�v�����B�Ō`������Ă���B�g����o�����킸�A�t�����X��̓ǂݏ������ł���A���̃R�����E�F���X�ɎQ���ł���B����M����|�p�ƁA�m���l�A���w�ҁA���l�A�T���ȏ����������A�c�_�����킵�Ă���B���̕��|���a����慎h�̉�������̐��_�W�����Ă���B
�@�X�B�́A�w���w�̗��j�x�ɂ����āA�ꔪ���I�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���݂̐��w�̂ǂ̕���ł��I�C���[�̖�����������{���������o�����Ƃ��ł���B�I�C���[�A�����ă��O�����W���A����Ƀ_�����x�[���܂ŕt��������A���݂ɋy�Ԑ��w�̍����́A�\�����I�ɂł����Ƃ�������B���w�ɂƂ��āA��{�I�Ȏ����̔����Ƃ����_����݂�A���̎���͍��܂ł̗��j�ō���������Ȃ��B�\�����I�́A���w�ɂƂ��āA�����̐��I�������̂ł���B
�@���łɁA���̎�̕W��Â�����A��r�̂��߂Ɏ��݂�A�\�����I�͌����̐��I�ł���A�\�㐢�I�͑̌n�̐��I�Ƃł��������ƂɂȂ낤���B���̐l�́A��\���I���Ȃ�Ƃ�Ԃ��낤�B����l�̂Ȃ��ɂ͂������@�̐��I�Ƃ�т�����l�����낤���A�܂��A����͂��ꂩ��̖��ł���B
�@�������A�����̌ʓI���������ɁA�\�����I���\������̂��������Ȃ��B���j�͂��ł����������A���̎���̎嗬�Ƌ��ɁA����̎嗬�ƂȂ�ׂ����ꂪ�n�܂��Ă�����̂��B�S�ȑS���h�́A���̎����𒁏��Â��͂��Ȃ��������A�\�㐢�I�����ł������B
�@�ꔪ���I�͈ꎵ���I�ɔ������ꂽ�u�����v�ɗ��r���A�u�����v��T���o���B����͊w�тւ̈ӎu�ł���B�[�֎�`�͒m���l�ɂ�閯�O�̖��m����̉���ł͂Ȃ��A���ׂĂ�m��s�����Ă�낤�Ƃ����ƒm�I�×~���̌����ł���B�[�֎�`�҂��������Ă������|���a�������ݏo�����ō����삪�S�ȑS���ł���B����̓G�v���C���E�`�F���o�[�X(Ephraim Chambers)�́w�S�Ȏ��T(Cyclopedia)�x(�ꎵ��)�ɉe������Ďn�܂�A�ꔪ���I���\����m�I�v���W�F�N�g�ł���B�S�ȑS���́u�S�w���ЂƂ̃T�C�N���ɓ������悤�Ƃ�����̂������B�������Ȃ���A����͂܂����n���Ă��Ȃ������B����ǂ��납�A�\�㐢�I�̒������镪�f�����̌�ɗ���̂ł���v�i�w���w�̗��j�x�j�B�S�ȑS���́u���ՓI�����̊O��ɂ�����ʓI�W�ρv�������A�ꔪ���I�̓�d����̌����Ă���B
�@慎h�̉���������u���ՓI�������v�Ɓu�����̑͐ρv�Ƃ�����ʐ��������Ă���B�m���ɁA���̎���́A�����I�ɁA�ꎵ���I�ɑ����Ă���B�������A���̐��_�͈ꔪ���I�̊@�������Ƒ�����ׂ��ł��낤�B
�@�ꔪ���I�́u�����̐��I�v�ƌĂ�邪�A���̗�����慎h�I�ł���B�[�֎�`�Ƃ���������`��慎h�Ƃ�������`�̝h�R�A���Ȃ킿���������̑Η��}���ɂ��ꔪ���I���߂��闝���͋ߑ�ɓł���Ă���ɂ����Ȃ��B�S�ȑS���́A慎h���l�A�Í������̒m���E�����܂Ƃߏグ�Ă���B�������A�f�[�^�E�x�[�X�ł͎g���₷�����D�悳���B�_�ł͂Ȃ��A���t�@�x�b�g���A���Ȃ킿���S�X�ɂ���ĕ���ɐ�������Ă���B�_�_�Ƃ���q�G�����L�[�͊������A�_���A�l�ԓ��l�A�����̍ق����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ꔪ���I�͐_���l�Ԑ錾��������ł���B�hKnow then thyself, presume not
God to scam; the proper study of mankind is man�h(Alexander Pope �hAn Essay on Man�h�U).
�@���̎����ɁA�C�M���X�������c��̏��F�Ȃ��ɐ����Ɍg���Ȃ��Ȃ����悤�ɁA���̐�ΓI�D�ʂ��͕���A�U�������ƕ����̒n�ʂ��l������B�h���C�f�����j�����l�D����Ȃ�������̕���Ŋ����ʂ�A���l�����ꂾ���ł��鎞��͏I���A�U�����肪���Ă����B�U���͊�����悵�A�W�������ɂ����܂��Ȃ��ɁA��Ƃ����͍�i�������܂����Ă���B�[�֎�`�҂̎U���ɂ̓��}���X��SF�A�t�@���^�W�[�A�A�i�g�~�[�A慎h�Ȃǂ���Ƃ�����W���������܂܂�Ă���B��]������������̃W�������Ƃ��Đ������Ă���B�����A�W�������Ƃ̋��E�͂͂����肵�Ă��炸�A��]�͓����ɑ��̉����̂��ł�����B
�@�Ƃ��낪�A��㐢�I�ɓ˓�����ƁA���Ԃ͈�ς���B�ߑ�͐_�ɗL�ߔ����������A���Y���Ă��܂��B�_�͎��̂ł���B
�@�X�B�́A�w���w�̗��j�x�ɂ����āA�J�[���E�t���[�h���q�E�K�E�X��p���āA�ꔪ���I�ƈ�㐢�I�̈Ⴂ�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u���p���w�ҁv�ł��邱�Ƃ��u�������w�ҁv�ł��邱�Ƃł�����A�u�����w�ҁv�ł��邱�Ƃ��u���w�ҁv�ł��邱�Ƃł�����Ƃ����Ӗ��ŁA�K�E�X�͍Ō�̏\�����I���w�҂ł������B�����ē����ɁA�u�������w�v�Ɏ��������Ӗ����������A����ꂽ��������̗��_�̌n�̒��ɒ��߂�������Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�K�E�X�����ŏ��̏\�㐢�I���w�҂ł������B
�@���l�ɂ��Č���Ƃł���A�Ȃ����|��Ƃɂ��Ĕ�]�Ƃł���悤�ȂƂ炦�ǂ���̂Ȃ����[�e�B���e�B�E���C�^�[�͈�㐢�I�ɂ́A������A�p�������B�������镪�����Ƃ��āA�K�v�ɔ����āA�T�܂������ɐG���ɂƂǂ܂�B
�@��㐢�I�A�_�������Ƃɂ��A�w��͍����z���ɋ��߂��Ȃ��B���g�ō����t���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���̈�ɂ����āA�ו����E��剻���i�ށB�̌n�̐��I�̂��̖��̒ʂ�A���ꂼ��̕���͎������A�̌n�����Ă����Ɠ����ɁA�����炩���͏����A�꒣�����邱�Ƃ��Öق̃��[���ƂȂ�B
�@�_�̎����}����ƁA�g����K�����u�����v�ւƏW�ꂽ�悤�ɁA�U���W�������́u����(Novel)�v�ɕW���������B�����A��萳�m�ɂ́u�ߑ㏬��(Modern Novel)�v�͑̌n�̕��w�ƌĂׂ悤�B����ȑO�ɑ��݂��Ă��Ȃ������ɂ�������炸�A�����͕��w�̎匠�͎��������ɂ���Ǝ咣����B�Ƃ͌������̂́A�����͎��獪���t���Ȃ���Ȃ炸�A��]�͂��̑㗝�l�Ƃ��ĎЉ�ɑi���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B��]�Ƃ͐E�ƂƂ��Ċm���������A���̑㏞�͑傫���B
�@�C��O�́A�C��O�����q���j�́w������p�x�ɏ�������Ă��颁q���_���E�A�[�g�r�Ƃ͂Ȃɂ���ɂ����āA�ߑ�|�p�ւ̔�]�̖����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�K���I�ی�������A����̏��i�Љ�A�L���Љ�ɓ������܂ꂽ���_���E�A�[�g�́A���i��������邱�Ƃ��ł����A���̍��ِ����������߂̂��Ƃ�(�錾�A�L��)�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���_���E�A�[�g�̓����ł���A���Ƃ̏d�v��������͗\�����Ă���B���p������قǂ�������̂��Ƃ����������Ƃ͂Ȃ������B���p�������āA�������邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���A�܂����Ƃ��������A���̂��Ƃɂ��Ȃ�����āA���p��i���������Ƃ����Ă����قǂ��B
�@���̂悤�ȁA���Ƃ�(�ϔO�A�L��)�̐�s�����炵�āA��]������܂łƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǑ傫�ȉe���͂����悤�ɂȂ�B��]���̓��_���E�A�[�g�̔閧���ɂ��錠�ЂƂ��ĐU�����悤�ɂȂ�B���_���E�A�[�g�͓���ł���A�ꕔ�̃G���[�g�ɂ���ĉ�ǂł���Ƃ����_�b�����肠������B
�@�|�p�́A�K���I�ی�������ƁA����́A���ՓI�ȁA�x�z�I�l���ł��邱�Ƃ���߂āA���q�^���r�ɉ�̂���B���_���E�A�[�g�́A�q�^���r�Ƃ����l�Ԃ��Ƃ�̂ł���B
�@����͌|�p�����ɋN�����ϗe�ł͂Ȃ��B�_�̎��ɂ����āA��]�͐V���ȗ��_�ɗ��r���鏬���̃X�|�[�N�X�}�����Ȃ߂��Ă��܂��B���̏����������Ӗ�����̂���ǎ҂ɉ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������ۂ����]�Ƃ��o�ꂷ�邪�A�ނ�͎��Ȃ���邱�Ƃɐ�S����B���̌��ʁA��]�Ƃɂ͋ɂ߂ċ������I�Ȓm����ߏ�Ȏ��ӎ��������K�{�ƂȂ�A�S�ȑS���I�Ȕ����͋��߂��Ȃ��Ȃ�B�o�D�̃Z���X����]�Ƃ̏�������O�����B
�@��Z���I�A�_�͎����Ǝv���Ă�����A�������u�ɂȂ���A���ՓI�ȈӖ��ɂ����āA�����Ă���Ƃ�����ł���Ƃ�������ɂȂ��Ă������Ƃ����o����B�ߑ�Ȋw�̐i���͒������B������_��DNA����ǂ��A���̃N���[����a��������ɈႢ�Ȃ��B�_�̎��͌���s�\�ɂȂ����̂ł���B
�@���@�̐��I�ł����Z���I�A�ߑ㏬���ɑ����āA���@�̕��w�Ƃ��ĂԂׂ��u���㏬��(Contemporary Novel)�v���嗬�ƂȂ邪�A����́u�����h���}(Melodrama)�v�ł���B�����ɑ����ăG�X�j�b�N�����o�����悤�ɁASF��t�@���^�W�[�A�~�X�e���[�A�T�X�y���X�A�z���[�Ȃǂ̃W�������̕������Ӗ�����B�������A��]�͈ˑR�Ƃ��ď����̎���Ɠ��l�̒n�ʂɊÂĂ���B�Ȃ�قǁA��]���g�����f��𗧂āA�V��]��\����`��]�A��e���_�A�t�F�~�j�Y�����_�A�J���`�������E�X�^�f�B�[�Y�Ȃǂ��܂��܂ȗ��_�����B���ꂼ��`���[�~���O�ł��邱�Ƃ͔ے肵�Ȃ��B����ǂ��A������`�ɐZ���肫��������l���Y�ݑ������w�N�A���ʂȎ����ꉮ����]�\���Ă���Ƃ����S�邽��L�l�ł���B
�@�ߑ�ȍ~�A慎h���w�̓`�����ȓ��{�ł́A�������M�ɍہA�L���Ƃ��Ă̑Ώ۔c������̎��ɂ���Ă���B�����]�Ƃ̒��ɂ́A�Ώۂ̌ŗL�����낭�ɏ����������Ȃ������Ƃ�ᔻ����ǂ��납�A���߂ł������ƂɁA�^����������҂܂ł���B��]�Ƃ́A�����ԂɁA���o�[�g�E�f�����@���ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@��Z���I�㔼�A����`�ւ̊S�̍��܂肩��w�ۓI�������{�i������B�܂��A�l�b�g�̔��B�͔����I�ȏ��𐢊E�K�͂ő̐ρE�g�U�����AE���|���a���������炵�Ă���A���͂�u���������̘b������(It is between you and me)�v���ʂ�ɐM����҂Ȃǂ��Ȃ��B����͏]���̔�]�ł͂Ȃ��A慎h�I�E�S�ȑS���I��]�̍ĔF���𑣂��Ă���B�hTrue wit is nature to
advantage dressed, what oft was thought, but ne�fer so well expressed�h(Alexander
Pope �gAn Essay on Criticism�h).
�@����ǂ��A���̔×��̒��A�����̔�]�Ƃ�����ɑΏ�������Ȃ��ł��邽�߁A�u���O�ȂNJ�������ۂ��v�����܂܂ɋL���̂���]�Ƃ��Ď�e����Ă���B���j�b�|�X�I慎h�̎��オ���������̂ł���A��]�̓��j�b�|�X�I慎h�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ�}�[�^�C�i�X�E�X�N���u�����X���m�́A�����Ȃ铪�]�ƖL�x�Ȋw���ɂ��n���̏�ŁA�����J���A�����f������ɈႢ�Ȃ��B�u����ɂ����čł��K�v�Ƃ���Ă���̂́A�w�������ϔ�]�x�A���Ȃ킿�����̌����Ƃ���́w�n�b�`�|�b�`�E�N���e�B�V�Y���x�ɂق��Ȃ�Ȃ��v�B
�@A little learning is a dangerous thing;
�@Drink deep, or taste not the Perrian
spring.
(Alexander Pope �gAn Essay on Criticism�h)
�q���r